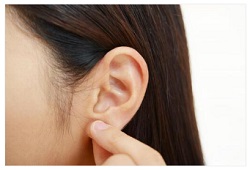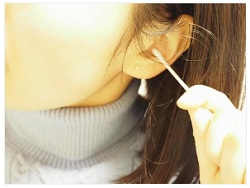このコンテンツでは難聴を引き起こすさまざまな原因やヘッドホン難聴についてまとめています。
「聴こえにくくなる」症状にも様々な原因があります。
予防可能な難聴もあるので参考にしてみて下さい。
様々な難聴の症状や原因 加齢や突発性 喫煙も(特に女性は要注意)
難聴で最も一般的なのは加齢と共に起きる難聴です。
加齢による難聴は、脳の聴覚神経や内耳の神経細胞が年齢とともに減少するために起きます。
発症年齢と症状の程度には個人差があります。
片方の耳が突然聞こえなくなる突発性難聴という症状もあります。歌手の浜崎あゆみさんも発症しました。(下の関連記事をご覧ください)
中年以降に多く、めまいなどを伴うこともあります。
ウイルス感染や疲労などが原因と考えられていますが、はっきりとしたことはわかっていません。
ストレスも原因になります。薬による治療を試みても、原因となるストレスを取り除かない限りは症状は改善しません。
いじめを受けていて、難聴にも苦しんでいた子供が、登校拒否した途端に難聴が治った例があります。
意外なことに喫煙も難聴の原因です。特に女性は影響が大きく、喫煙するほど聴覚の老化が加速されるとの報告もあります。
ヘッドホン難聴 音量の上限や対策は?
大音量の音楽をヘッドフォンで長時間聴き続けると聴力が落ちることがあります。
こういった難聴を伝音性難聴といい、ヘッドフォンによるものは若い人に多く、かつ回復が難しくなります。

オーストラリアの国立音響研究所が05年の夏発表した研究結果によると、ポータブルプレーヤーを使用している人の約25%は、聴覚障害を起こしてもおかしくないレベルの騒音にさらされています。
ヘッドホンの音量は60%のレベルで1日1時間以内なら比較的安全とされています。
携帯型のデジタルオーディオプレーヤーがスマートフォンが普及し、街中でもイヤホンを着けて音楽を聴く人が増えています。
中には、外部に音が漏れるほどの大音量で聴いている人もいます。こうした行為は、公共交通機関では周りの迷惑となるだけでなく、聴いている本人の耳にもダメージを与えています。
日経プラスワンヘッドホン難聴の防ぎ方など
2011年4月2日の日経プラスワンに、ヘッドホン難聴に関する記事がありました。
ポイントを箇条書きでお知らせします。
・有毛細胞には「感覚毛」があり、有毛細胞および感覚毛は非常に繊細で、一度抜けたり、傷ついたりすると再生しない
・つまり、聴力を失うと回復するのはほとんど不可能(慶応大学医学部耳鼻咽喉科 小川 郁教授)
・国の労働安全衛生のガイドラインでは、85デシベルの音を8時間以上聞かないよう定めている

ヘッドホン難聴を防ぐ具体的な対策としては、次のようなものがあります。
・耳の聞こえ方に違和感を感じたら、病院へ行く
・電車などの中では、音量を大きくしすぎない
・ヘッドホンメーカーのオーディオテクニカは、電車など周囲が騒がしい場所では、耳栓のように装着するタイプのヘッドホンを勧めている 外部の音を遮断することで、小さな音でも明瞭に聞くことができるから
・また、ノイズキャンセリング機能がついたタイプも良い 列車の走行音など、不要な音が除かれるので、必要な音が耳に届きやすい
・85デシベル以上の音量が出ないタイプのヘッドホンも発売されている 英語の勉強や、ゲーム機を使う子供の耳を守るためにも使用を検討する価値あり