 最近は男性でも便秘になる人が増えているそうです。
最近は男性でも便秘になる人が増えているそうです。
その原因のひとつに停滞腸があります。
停滞腸のチェック項目10個 5個以上当てはまったら要注意!
停滞腸とは、ぜん動運動などの動きが悪い腸のことです。
食べたものの消化・吸収・排泄がうまくいかなくなり、お腹が張る、排泄しても便が残った感じがする、といった症状が出ます。
便秘の前段階でもあるので、停滞腸が続くと排便の回数が減っていきます。
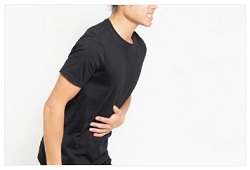
平石クリニックの平石貴久院長は「停滞腸のチェック項目」を作っていて、停滞腸の度合いを知る目安としています。
そのチェック項目を紹介します。
以下の設問にYesかNoで答えて下さい。
2 野菜はあまり好きではない
3 果実はあまり食べない
4 あまり水分をとらない
5 1日3食とらないことが多い
6 食後、もしくは普段から下腹部がぽっこり出ている
7 最近ダイエットをした(またはしている)
8 あまり運動しない
9 最近ストレスを感じることが多い
10 最近便秘気味だ(またはいつも便秘)

Yesの数が
・0~2個ならほとんど問題なし
・3~4個なら軽度の停滞腸
・5~7個は中程度の停滞腸
・8個以上なら重度の停滞腸
と判断されます。
5個より多い場合、食物繊維を多く摂取するなど食生活の改善や、適度な運動の実践といった生活習慣の改善の余地があります。

私としては、便秘対策にはとりあえず純ココアを飲むのがおすすめです。
私の場合は飲んだ直後に出ることもしばしばあります。
身体の冷えと便秘 松生恒夫医師の本から
少し前に、松生恒夫(まついけ つねお)医師の「冷やさない「腸」健康法」という本を読みました。
大腸内視鏡検査が専門の松生医師は、便秘外来も開設されています。

松生医師は多くの患者を診察する過程で、「便秘には、身体の冷えも大きく関わっているのではないか」という疑問を持ったそうです。
その疑問を基に調査を進め、その結果と具体的な対策をまとめられたのが上の本です。
「はじめに」の章にわかりやすい例が挙げられていました。
以下に引用させて頂きます。
手足はもちろん、お腹の冷えに苦しむ患者さんもいます。
そこでデータをとってみると便秘外来に来た患者さん126人のうち、冷えを訴える人が88人という結果が出ました。
これに驚いた私は、本格的に冷えと便秘の関わりを調べることにしたのです。
やがて少しずつですが、冷えと便秘の関連が見えてきました。冷え性の人には便秘の訴えが多いという研究報告も見つかりました。
真冬や、エアコンで体が冷やされる夏に、便秘外来に来る患者さんが急増するという事実。
また、同じヨーロッパの中でも潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患は、スウェーデンやデンマークなど寒い国に多いのです。
(中略)
一方、冷えを訴える患者さんを温めるような処置をしてあげると、確かに便秘がよくなるのです。
(中略)
最新の栄養学から導き出した、「体を温め、腸の動きをよくする食材」厳選して摂ってもらったのです。
これが非常にうまくいき、「便秘の改善とともに冷えも解消された」という、うれしい声を多数、いただけるようになったのです。
本では、身体を温めるためのおすすめ食品が紹介されています。
便秘対策というと、これまでは「食物繊維をとる」「水分をとる」「適度な運動をする」などが強調されてきましたが、「体を温める」やり方は、あまり注目されていませんでした。(この本の初版は2010年1月20日発行です)
便秘に悩まされている方は、機会があったら一度目を通してみてはいかがでしょうか。
- PR:Amazon
- 冷やさない「腸」健康法―自分でできる 新「腸内リセット」
安易に便秘薬(下剤)を使うのはNG 便意を感じなくなる 回復は大変!
「出なくなっても、便秘薬(下剤)を使えばOKなのでは?」とお考えの方はいませんか?
私としては、便秘薬を安易に使うのは絶対反対です。
上で紹介した「冷やさない「腸」健康法」の著者、松生医師も全く同じ警告をされています。

松生医師の調査では、下剤の服用期間が長い人ほど便意の消失が起こりやすいことがわかっています。便が直腸に達しても、便意を感じなくなるのです。
腸の働きでなく、下剤の作用で便が排出されるため、腸が鈍感になり、働かなくなってしまうのです。
松生医師は、この現象を「内臓感覚障害」もしくは「内臓感覚低下症」と表現されています。
腸の働きが鈍って便が出ないため下剤を使い、下剤を使うとさらに腸の働きが弱る、という悪循環に陥ってしまいます。

それでは、内臓感覚低下症はどのように治療するのでしょうか?
松生医師によると、治療法は医学の教科書にはほとんど書かれていないそうです。
そのため、松生医師も試行錯誤ながら治療法を模索しています。
便意を回復できる例も少しずつ増えていますが、それでも平均6ヵ月ほどの時間が必要です。症状を改善させるのは大変なのです。
何より大事なのは下剤を軽々しく使わず、内臓感覚障害を防ぐことです。
排泄は生理活動です。人間が本来持っている力で行うのが自然な姿です。


