 狭心症・心筋梗塞では胸痛が起こります。
狭心症・心筋梗塞では胸痛が起こります。
症状が起きているのは心臓であるにも関らず、狭心症では心臓の一点だけではなく広い範囲で痛みが起きます。
また心筋梗塞では、「痛み」以外の症状が起きることもあるようです。
狭心症の症状の表れ方 痛む場所は心臓に限らずいろいろ
狭心症で痛みが起きる場所は広範囲にわたり、あご、のど、胃、さらには左肩や背中が痛む場合もあります。
痛む場所がこれほど違うのは、心臓から脳まで痛みを伝える神経が、他の部分(あご、のどなど)からの神経と共通しているためです。
痛みの信号が「混線」してしまうのです。
狭心症では、
・息が詰まる感じ
・絞めつけられるような
・押しつぶされるような
・焼きつくような
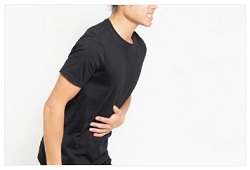
といった、こもった感じの痛みが特徴的です。「チクチク」といった軽いイメージとは違います。
狭心症では2~3分から10分ほど痛みが続き、ニトロ剤が有効に作用します。狭心症で痛みが15分以上続くことはまずありません。
心筋梗塞の症状 「痛い」よりも「苦しい」
心筋梗塞では「痛い」よりも「苦しい」「重い」と表現されることが多いようです。
めまいや吐き気、呼吸困難といった症状が表れることがあります。特に高齢者や糖尿病患者では痛みを伴わない急性心筋梗塞が多くなります。
寒い日の朝、入浴の前後、飲酒後、真夏の脱水状態は発症しやすいので注意しましょう。
心筋梗塞ではニトロ剤が効かず、10分以上、時には2~3時間以上痛み・違和感が続きます。
女性が心筋梗塞を発症すると死亡率が高い
 女性が心筋梗塞を発症すると、死亡率が男性より3倍高くなります。
女性が心筋梗塞を発症すると、死亡率が男性より3倍高くなります。
熊本心筋梗塞研究会が熊本で調査した結果ですが、この傾向は全国的なもので、さらには海外の統計でも同様の結果が出ています。
医学的な理由ははっきりしていません。
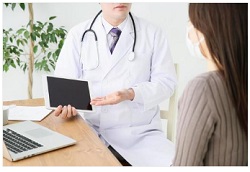
熊本での調査では、発症者に対する死亡者の割合は男性で4.34%に対し、女性は12.23%と3倍近くも高くなっています。
女性は閉経後、コレステロール値が血液1デシリットルあたり20mg程度上がること、男性より痛みに強いため医療機関の受診が遅れるケースが多いなどが原因として考えられています。
大豆食品たくさん食べる女性は脳梗塞や心筋梗塞になりにくい ただしサプリは
 津金昌一郎国立がんセンター予防研究部長を中心とした厚生労働省研究班の調査によると、大豆をたくさん食べる女性は、脳梗塞や心筋梗塞になりにくいことがわかっています。
津金昌一郎国立がんセンター予防研究部長を中心とした厚生労働省研究班の調査によると、大豆をたくさん食べる女性は、脳梗塞や心筋梗塞になりにくいことがわかっています。
この傾向は、閉経後の中高年女性で特に顕著でした。
大豆のイソフラボンが女性ホルモンに似た作用を持つため、動脈硬化を防ぎ、心筋梗塞などの循環器疾患の発症リスクを下げると考えられています。

ただし大豆イソフラボンだけをサプリメントなどで過剰に摂取すると、閉経前の女性では月経周期の乱れや子宮膜増殖症などのリスクが高まることが報告されています。
また閉経後の女性も、大豆イソフラボンの過剰摂取を長期にわたって続けると子宮内膜増殖症の発症率が上がるという調査結果もあります。
大豆イソフラボンは納豆や豆腐などの食品から適量摂取するのが好ましいようです。

