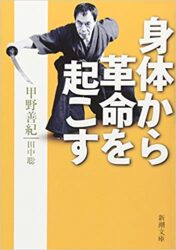甲野さんが考えるに、前ページ・スポーツの筋トレでは技術向上しないの最後で挙げた動作で作った身体は「多機能」です。
多機能な体は、ウェイトトレのような限られた動作では作られません。

関連して、子供の運動能力を育てる場合でもひとつのスポーツをさせるより、いろんな動作をする「外遊び」が良いとする説があります。
「石を運ぶ」などの労働で多機能に そんな機会がない現代では…
「多機能」な体とは「様々な動きに対応できる体」とも言い換えられます。
持ちやすいバーベルとかじゃないんですから、ウエイト・トレーニングで作った身体とは、ぜんぜん違うんですよ。
石を動かすことが目的なのと、身体を作るためにという頭で目的をつくってそのために身体を使うのではどうも根本的な何かが違うのでしょう。
(39ページ)
とはいえ、現在は「子供が石を運ぶ労働」という機会自体が少なくなっています。
それではどうすれば良いのでしょうか?
外遊びで子供の総合的な運動能力を育てる
東京大学大学院教育学研究科の武藤芳照教授は、
子供のうちから特定のスポーツばかりをやらせるのは良くない。外で遊んで総合的な運動能力を発達させるべき。
と主張されています。「多機能」という点で甲野さんの考え方と近いものがありますね。

もしもあなたがスポーツをやっている、あるいは子供さんにスポーツをやらせようと考えているなら、
「小さい頃から(同じ)スポーツをずっとやっています(あるいはやらせるつもりです)」
「筋肉トレーニングを積極的に取り入れてます」
といった方針は、必ずしも正解ではないかもれません。
何かのスポーツのトレーニングで「特定の○○」を鍛える、あるいはずっとやる、だけでなく
「いろんなことをやる」
「身体全体を使ってやる」
ことを心掛けた方が、結果的にはそのスポーツの技能向上につながる可能性もあるということです。

実際に、甲野さんの考え方をとり入れているアスリートは非常に多く、そのスポーツの種類も多岐に渡ります。
プロ野球の桑田真澄投手をはじめ、女子バスケットボール日本代表の濱口典子選手、卓球の平野早矢香選手などが甲野さんの指導を受けていて、さらには
楽器演奏 舞踊 介護医療 工学
といった分野にまで甲野さんの考え方が応用されています。
スポーツに限らず、甲野さんの考え方をかじってみると新しい発見があるかもしれません。
ところで、甲野さんと言うと「ナンバ歩き」を連想する人も多いのではないでしょうか。
次のページでは「ナンバ」について紹介します。
- PR・Amazon
- 表の体育 裏の体育 日本の近代化と古の伝承の間に生まれた身体観・鍛錬法
- 古武術for SPORTSキッズ編―動けるからだの作り方
- DVD付 古武術for SPORTS いきなりスポーツが上手くなる!
- 写真と図解 実践! 今すぐできる 古武術で蘇るカラダ (宝島社文庫)