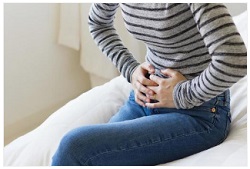前のページ「油ものが苦手になるのはカロリー制限を求める体のサインでは?」はこちら
身体が出す「拒否反応」は、アルコールに対しても言えるのではないでしょうか。

ある程度の年齢に達すると、お酒も弱くなってきます。これも油ものと同様、身体の拒否反応ではないでしょうか。
アルコールの分解は体への負担が大きい
二日酔いの日に、お酒を飲みたいとは思いませんよね。
二日酔いはアルコール拒否の最たる状態であって、そのマイルドなのが「お酒をあまり飲めなくなった」状態だと考えています。
これまで私は週に1~2回飲酒していましたが、ここ1か月ほど全く飲んでいません。
あまり飲めなくなったと実感しているため、試しに飲酒を一切やめてみたのです。飲むのはノンアルコールばかり。
そのおかげか、最近は体調がすこぶる良いです。
日本人は、お酒を全く受け付けない人もいます。日本人に多い「ある程度は飲める人(私はコレです)」でも、アルコールの分解は身体への負担が大きいはずです。
なので、そんな人が「飲めなくなった」と感じたら、試しに酒量をグッと少なくするか、ゼロにしてみてはいかがでしょうか。
体の負担が減り、消耗しなくなって体調の改善が実感できるでしょう。
体からのサインは意外と多い どう行動に移すか
私の推測ですが、昔の人はこういうサインに敏感だったのではないでしょうか。
「お酒はホドホドに」
「砂糖の食べ過ぎはダメ」
「夜食は良くない」
「薬も使いすぎると毒になる」
「旬のもの、地のものはイケる」

鋭い感覚から多くの経験が生まれ、それが重なって数々の健康ことわざが生まれたのでしょう。
漠然とした感覚的なサインだけでなく、わかりやすいサインも多くあります。
お腹が出てくる
ヒザや腰が痛くなる
肌が荒れる
気持ちが沈みがちになる
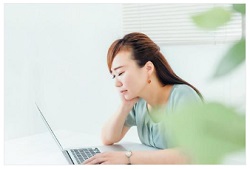
・・・などなど。
健康診断の数値の変化などはサインそのものです。
身体のサインを認識するには検査技術の発達した現代の方がはるかに恵まれています。
問題は、その「サイン」をいかに解釈し、行動に移すかにかかっているわけです。

行動としては、「何かを食べなくなる」かもしれないし、「食べるようになる」こともあるでしょう。「適度に運動をする」かもしれません。
実は、私はいまでも油っこいものは大好きです。
これを書いている最中も、「トンカツ食いてぇ・・・」と考えてるほどです。だからといって、油っこいものをしょっちゅう食べるのは控えています。
身体のサインを無視して食べ続けていると、いつか「油もの絶対NG」な病気を引き起こしそうだからです。
好きなものは、いつまでも食べられる身体でいたいですからね。
拒否反応など体のサイン 終わり。